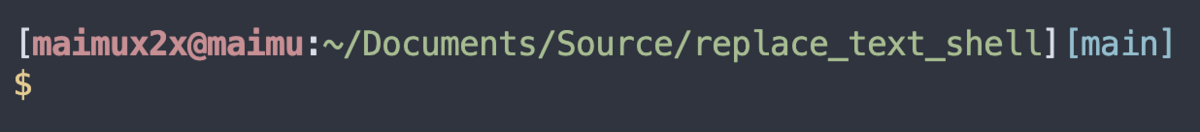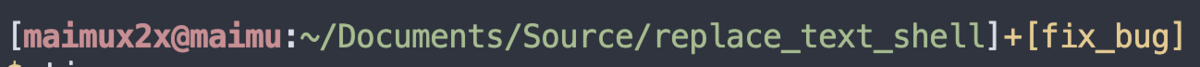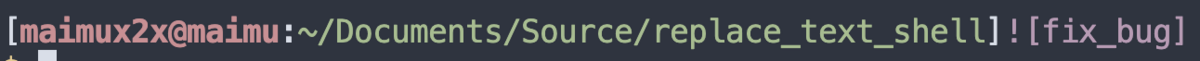2024年3月1日と2日にSTORES株式会社様のオフィスをお借りしてRails Girls Tokyo 16thが開催されました。
今回、STORESのえんじぇるさんと一緒にオーガナイザーを務めたため、開催の経緯から開催後の振り返りまでをまとめたいと思います。

railsgirls.com
開催の経緯
今回自分がオーガナイザーを務めてTokyo 16thを開催したいと思った一番のきっかけは、昨年Rails Girls ガイドの翻訳に取り組んでいたことでした。
この取り組みについて、昨年の9月に開催された大阪Ruby会議でLTをしたのですが、発表後に過去に大阪でRails Girlsを開催された方や会場を提供いただける企業の方とお話をして、東京での開催を自分がやるということについて初めて意識しました。
ただ、自分はこれまでRails Girlsのワークショップに一度も参加したことがなかったため本当にやるかは少し考えました。
数週間どうしようか考え、とりあえず一度相談してみようとRails Girlsのslackで東京開催をやってみたいと江森さんにご連絡をしたところ、少し前に別の方からも東京開催の相談をもらっていると返信をいただき、それがえんじぇるさんでした。
えんじぇるさんとはRubyコミュニティで何度もお世話になっていて、一緒に開催できる運びとなり、とても嬉しかったことを覚えています。
ロゴ制作について
いざ開催に向けて動き始めたのは2023年12月中旬ごろでした。
まずは16thのサイトを用意する必要があったため、ロゴをどうするかという部分からえんじぇるさんと相談して準備を始めました。
ロゴの制作は一緒にSTORESさんのイベントやRubyコミュニティのイベントに参加していたデザイナーのmoegiさんにお願いすることになりました。
ロゴの制作をお願いするにあたって、16thのテーマをえんじぇるさんと話し合い、「プログラミングへの入り口」というイメージを表現することに決まりました。
それをmoegiさんに伝えた結果、2つの案を出してくれ、虹のアーチのデザインが16thのロゴに決まりました。
ロゴの制作についてはmoegiさんのブログに詳細が書いてあるため、ぜひご一読ください!
divka-design.com
サイトについて
ロゴが決まったら、サイト制作です。
サイトについては過去のサイトに則って作成するため、時間はかからずに公開自体はできたのですが、Xでリンクをシェアする際にOGP画像が表示されるように変更しました。
過去のRails Girlsのロゴも全て可愛いのにOGPが設定されておらず、Xで投稿した際にリンクのみの投稿になっていたことがもったいないと感じていたためです。
(OGPについてはTokyo開催のサイトを回ごとに内容を更新しているため、次の回に更新すると過去の投稿のOGPが最新の内容に更新されて表示されてしまうという問題はありそうです)
今回、OGPを設定してXで16thのサイトをシェアした結果、公開当初からロゴが可愛い!と反響があり、視覚的な効果は大切だなと感じました。
参加者の募集について
サイト公開と同タイミングで参加者とコーチの募集を開始しました。
コーチについては日頃からお世話になっているRubyコミュニティの方々が協力してくれると思ってあまり心配はしていなかったのですがw、参加者の方については可能であれば普段SNSなどのインターネットをあまりやっていない層の方にもRails Girlsのことを知ってほしいという思いがあり、ポストカードサイズのチラシを作成して知り合いに配ったり、自分の通っている陶芸教室の棚に置かせてもらったりしました。
STORESさんのオフィスでもチラシを置いていただき、参加応募いただいた方の中にチラシ経由で申し込んでくださった方もいらっしゃいました。
今回のチラシ経由で応募いただけることももちろん嬉しかったのですが、申し込みをされなくてもIT業界に普段近くない方の目に触れる機会を作れたため、何かのきっかけで思い出したりしてもらえたらさらに嬉しいなと思います。
参加者については当初15名の枠で考えていたのですが、最終的に60名近くの方からご応募をいただきました。
えんじぇるさんが会場の収容人数を検討してくださり、20名で調整しようということになりました。
開催当日に向けて
今回、オーガナイザーがえんじぇるさんと私の2名だったため、年明けから2週間ごとに定例を行なって準備を進めました。
お互い日中は仕事があるため、少しでも動きやすくなればと思い、定例前日にアジェンダを共有し、話したいことを事前に確認できるようにしたり、期間を区切っていつまでに何を終わらせておくかをチェックできるタスク一覧を作成し、抜け漏れが発生しないことを意識して自分は取り組みました。
タスク一覧については、過去のオーガナイザーであるりほやんさんのブログがとても参考になりました。
rlho.hatenablog.com
また、今回コーチとしてご協力いただいた15thオーガナイザーのえりりんさんのブログも東京の一番直近の開催事例としてとても参考になりました。
note.com
えりりんさんは16thのイベント終了後にすぐに振り返りブログを書いてくれました!ありがとうございます!!
ブログの中でメッセージの発信について触れてくださっているのですが、実はXでの投稿はかなり意識してやっていました(気がついてくださり、ありがとうございます!)
note.com
ワークショップ中に開催の風景をXで投稿するのはもちろんなのですが、開催前からRails Girls Tokyo 16thが始まるぞ!という熱量?を上げていきたかったため、タイミングを見てsuzuriでのアイテム販売の告知やコーチ・スタッフに関するお知らせ、1週間前の呼びかけなどを投稿していました。
開催に向けた事前準備はえんじぇるさん、moegiさん、江森さんとうまく連携が取れて大きな問題は発生せずに進められたのではないかと思います。
コーチの皆さんとの準備
Rails Girlsのワークショップは参加者の方に1名ずつコーチがつきます。
今回も参加者の方の人数に合わせてコーチのご協力を募り、たくさんのRubyコミュニティの方が手を挙げてくれました。
コーチが確定した後、「素振り」と題して、オンラインで1時間半程度の打ち合わせを実施しました。
素振りの際は
- 関係者の自己紹介
- チーム編成の共有
- コーチをする際の注意点
- ガイドのポイントを確認
を行いました。
時間配分の調整は江森さんがいい感じにまとめてくださった部分が大きかったのですが、自分はいつも通りドキュメントを作成して、そこに共有事項やメモを残し、後で読み返せるようにだけしておきました。
コーチ素振りに参加ができず、当日を迎えるコーチの方も数名いたため、共有用のドキュメントは何かしら用意しておくと良さそうと思いました。
開催1週間前
江森さん主催のRails Girls Tokyo more!にえんじぇるさんと一緒に現地参加し、事前確認を行いました。
開催直前に実際に顔を合わせて会話ができたのはとても良かったです。
Rails Girls Tokyo more!は不定期で江森さんが主催されているオフラインのイベントなため、今回のRails Girlsのワークショップに参加が叶わなかった方や参加されて継続的にプログラミングやコミュニティと関わりを持ちたい方にはとてもおすすめの勉強会です!
いざ開催初日!
2ヶ月半ほどの準備を経て、あっという間にRails Girls Tokyo 16thのインストールデイがやってきました。
ロゴを制作してくれたmoegiさんがRails Girlsやチーム名のパネル、写真撮影用のpropsやスクリーンに投影するスライドのテンプレート一式を作成してくれ、16th全体のデザインが統一されて会場の雰囲気を作り出すことができたと思います。
こちらから声をかける前に積極的に意見を出してくれて、本当に感謝です。
また、えんじぇるさんが会場の整備や必要な備品・飲食物の手配を進めてくださり、会場設営もとてもスムーズに進めることができました。
ワークショップが始まってからは、コーチの皆さんが参加者の方をしっかりサポートしてくださり、とても安心感がありました。
同時にオーガナイザーである自分は見守り、何かあった際のサポートとしての動きに周り、ちょっと緊張気味で会場の隅っこにいましたw
開催2日目
2日目はインストールデイに参加ができなかった方の環境構築のサポートからスタートしました。
全員の環境構築が終わったら、いよいよWebアプリ構築の本編がスタートです。
ワークショップに進む前に開会の挨拶の時間をいただき、Rails Girlsについてや当日の流れなどを説明させていただきました。

Organizer LTをやらせていただくことになり、Before Rails Girls After Rails Girlsというタイトルで発表をしました。
私はRails Girlsのワークショップに参加をしたことはないものの、2022年の年末に開催されたRails Girls Gathering Japan2022というイベントが初めてのRails Girlsとの関わりで、そのイベントに参加したことがきっかけでいろいろな変化があったため、それを前半に話して後半は16thのワークショップに参加して終わりはもったいない!という内容のことを話しました。
参加者の方からも感想の声をかけていただき、嬉しかったです。
speakerdeck.com
Webアプリの構築がスタートしてからは、またまた見守り&飲食物の用意など裏方に周りましたが、集中してワークショップに取り組むGirlsとコーチの背中を見て、自分も混ざってコードを書きたくなりむずむずしていましたw
午前中のワークショップの時間が終わったら、ランチタイムです!
えんじぇるさんが選んで手配してくれたお弁当はどれも美味しそう・・・!!


また、ランチタイムの時間を利用してスポンサーLTも行いました。
タイマーを用意して時間を測り、時間が来たら終了!のLTらしい時間となりましたが、どんな事業をされているのかやそこで働かれている方のいろいろな内容の発表を聞くことができ、有意義な時間となりました。
ランチタイム後は再びWebアプリ構築のワークショップです。
時間の都合もあり、最後は少し駆け足にさせてしまった部分もあったかもしれませんが、Girlsの皆さんがアプリの構築を完了させてチームメンバー全員で集合写真を撮る瞬間は胸熱でした!
ワークショップ終了後はお楽しみのアフターパーティを行いました。
江森さん、hogelogさん、chobishibaさんにコーチLTをしていただきました。
chobishibaさんがクリエイティブコーディングで16thのロゴを作成してくださり、そのRubyのコードの中には今回チーム名に使用した「Proc, Array, Hasy, Integer, String」クラスが使われていますというお話をしてくださったのがとても印象的でした。
スライドも公開されているため、ぜひ内容を見てみてください!
また、我らが松田さんのコミュニティについてのいい話も聞けて、気持ちがいい感じに高まり、参加者同士での会話も盛り上がりました。
アフターパーティでは自分と同様に社会人になってからプログラミングの勉強をしてみたいという方も多数いらっしゃり、どんなふうに勉強をしてきたか話したり、歴代のRails Girlsオーガナイザーで集合写真を撮ったり、いろいろな話ができて自分もとても楽しかったです。

反省点
開催に向けていろいろ準備をする中で反省点も多数ありました。
反省点1
Rails Girlsのワークショップのサイトは全世界共通のRails Girlsのリポジトリで管理されています。
自分はそこに日本語でPRを出していました。
途中でRubyコミッターの柴田さんが英語でPRを出そうと声をかけてくださったおかげで気がつくことができました。
反省点2
コーチ・スタッフ用のTシャツの発注枚数を間違えました・・・(1枚足りなかった、ごめんなさい)。
飲食物や備品の手配はえんじぇるさんやmoegiさんが対応してくれていたのですが、自分が唯一手配したTシャツの枚数を間違えるとは・・・。
反省点3
ペース配分が最初はよく分からず、一人で突っ走ってしまいました。
昨年の12月に準備がスタートした際、まずはサイト公開!と思ってギア全開で突っ走ってしまったため、もう少し何をやるかどう役割分担するか、どんなスケジュールで進めるかを一番初めに整理してから動き始めるべきだったなと反省しています。
反省点4
スタッフとして協力してくれた2人への事前説明が不足していました。
今回、フィヨルドブートキャンプからすずかさんとmotohiroさんがスタッフをやりたいと自ら手を挙げてくれ、ご協力をお願いすることになったのですが、コーチは素振りとして事前の打ち合わせがあったのに、スタッフのお二人へは当日にお願いすることを話して動いていただいたため、事前にもう少しタスクリストなどを作成して共有した方が良かったなと感じました。
色々反省点はあるものの全体を通しては、たくさんの方が協力してくださったおかげで大きな問題が発生することなく、2日間を終えることができたと思います。
全体を振り返って
はじめは迷ったもののオーガナイザーの一人としてRails Girls Tokyo 16thを開催することができて本当に良かったなと思います。
開会の際にも話した通り、オーガナイザーの願いとして今回のRails Girlsのワークショップへの参加が参加者の方々の何らかの良いきっかけになったらとても嬉しいなと思っています。
プログラミングに興味はあるけれど、どのように勉強したり向き合ったりしたらいいか分からないという声も開催中たくさん聞いたため、少し前までエンジニアじゃなかった私は何かしらの形でこれからも情報発信だったり交流できる機会に顔を出したりして、誰かのきっかけになれたらいいなと思ったりしました。
Special Thanks!!!!
えんじぇるさん
一緒にオーガーナイザーができて、とても良い経験をさせていただきました!
コーチ素振りの際に準備はほとんどmaimuさんがやってくれましたと話されていましたが、そんなことないです!
えんじぇるさんが昨年Girlsとして15thに参加した際のことを共有してくれたおかげで準備することが明確になったり、会場の整備やカメラマン、案内スタッフの協力のお願いなどを進めてくださったおかげでとてもスムーズに準備ができたと思います。
また、飲食物やおやつのチョイスが流石でした😍
moegiさん
ロゴをはじめ、デザイン全般をディレクションしていただき、ありがとうございました!
moegiさんのロゴのおかげで16thのテーマがとてもいい感じに表現できたと思います。
手作りの撮影用propsも可愛かった〜!
江森さん
適度にオーガナイザーに進行準備を任せてくださりつつ、素振りでのコーチへの説明やスポンサー企業様とのやりとりをまとめてくださり、ありがとうございました!
コーチの皆さん
Umemotoさん、eririnさん、Koshibaさん、Minamiyaさん、Teraiさん、betaさん、nekoさん、rotelstiftさん、Shimojuさん、Kudoさん、Toriiさん、Harunaさん、Pinさん、Tumichanさん、16bitさん、Risaさん、HolyGrailさん、hogelogさん、Shiaさん、zanakaさん、Fujimuraさん、ヨヨイさん
2日間に渡りGirlsの皆さんをサポートいただき、ありがとうございました!
(私もGirlsに混ざって教わりたいほど、親身なサポートでした!)
スタッフの皆さん
すずかさん、motohiroさん、STORES社員の皆様
当日その場でお願いすることが多い中、たくさんご協力いただき、ありがとうございました。
スポンサー企業様
開催をサポートいただき、ありがとうございました!
参加いただいたGirlsの皆さん
2日間という長丁場に渡り、イベントにご参加いただき、ありがとうございました!
ぜひまたコミュニティでお会いしましょう!!